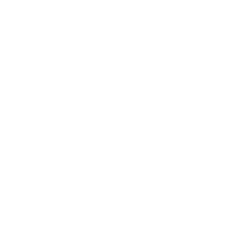 子宮のがんについて
子宮のがんについて
子宮頸癌とは?
子宮頸癌は子宮頸部(子宮の入り口の部分)に発生する癌です。女性生殖器癌の中では子宮体癌に次いで頻度が高い疾患です。扁平円柱上皮境界(SCJ)に多く、組織学的には扁平上皮癌が85%、腺癌が10%を占めます。近年HPV(ヒトパピローマウイルス)との関連性が明らかになりました。多産婦に多く、若年者も少なくないのが特徴です。
- 30~60歳に多い
- 接触出血(性交渉など)などの不正性器出血が見られる
- 子宮頸部細胞診にて、異常を認める
- コルポスコピーにて異常な移行帯所見(赤点斑、モザイクなど)、浸潤癌所見と認める
- 狙い組織診にて、扁平上皮癌、腺癌などが認めるとき
子宮頸癌と診断されるときには上記のような所見を認めることがあります。
子宮頸癌の多くは、定期的な健診で早期の発見が可能とされています。子宮頸癌は一般に異形成と呼ばれる前癌病変から上皮内癌になり、浸潤していくとされています。定期的な子宮頸癌のチェックはこれらの段階の早い時期で発見することが狙いなのです。
*異形成のすべてが、いずれ癌になるわけではありません。
なにが原因なの?
HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が大きく関わっていると考えられています。子宮頸癌の頻度自体は減少傾向にありますが、性交渉の低年齢化と多様化によって、若年者においては感染の機会がむしろ増えており、若い人の子宮頸癌は増加傾向にあります。
どうしたらいいの?
定期的に細胞診(子宮がん検診)を受けます。これは子宮頸部の細胞に悪性に変化しそうなものが無いかチェックするものです。20歳以上は定期的に細胞診(子宮がん検診)を受けたほうがいいでしょう。
子宮頸部の細胞診(一般には、子宮がん検診)の結果は下記のように表示されます。
■NILM:異常なし(陰性)
■ASC-US:意義不明な異型扁平上皮細胞
■ASC-H:HSILを除外できない異型扁平上皮細胞
■LSIL:軽度扁平上皮内病変
■HSIL:高度扁平上皮内病変
■SCC:扁平上皮癌
子宮頸癌は一般に異形成と呼ばれる前癌病変から上皮内癌になり、浸潤癌となります。異形成のすべてが、いずれ癌になるわけではありません。
また若い時期にHPVワクチンを打っておくことは子宮頸癌を防ぐきわめて有効な方法です。
*接種後も検診は必要です。
検査で異常が出たらどうしたらいいの?
細胞診によって子宮頸部に病変が疑われたら、次の段階の検査(コルポスコピー・組織診)が必要です。この場合には高度専門医療機関への受診が必要になります。また必要に応じて、子宮頸部円錐切除術が施行されることもあります。これは子宮頸部の入り口部分のみをくりぬいて、顕微鏡で調べる検査です。当クリニックでは細胞診の次の段階の検査や治療は行っていませんが、信頼できる医療機関をご紹介いたしますのでご安心ください。細胞診はそのやり方や、病気がある場所によってばらつきが出てくる可能性があります。適切な部分の細胞が取れていない可能性に関しては常に念頭に置いておく必要があります。
子宮体癌とは?
子宮の内膜に発生する癌のことです。腺癌というタイプの癌であることがほとんどです。好発年齢は50歳代であり、多くの場合に不正出血を認めます。近年増加傾向にあり、子宮の癌では一番多い癌です。
どんな人がなりやすいか?
好発年齢:40~60歳代
肥満・不妊・未経産婦に多いとされます。無排卵周期症・多嚢胞性卵巣症候群などの既往、高血圧、糖尿病の場合もリスクが上昇します。
診断方法
診断方法:子宮内膜組織診
子宮体癌は不正性器出血があることで疑われることが多く、経腟超音波検査で子宮の内膜が分厚くなっている場合には検査が勧められます。
また子宮内膜増殖症という状態を経由するタイプの癌が多くを占めます。
子宮体癌の症状
初期には痛みはなく、閉経後の不正性器出血が主な症状です。少量の出血の場合は、褐色から黄色帯下になり、子宮内感染を伴うと膿性になります。癌が子宮体部を超え、骨盤内組織に広がると痛みを伴ってくることがあります。






